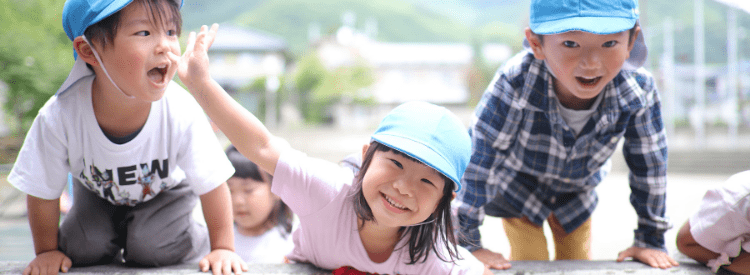子ども達と私達の笑顔のために
副園長だより芙蓉園だより芙蓉園は上田市街地の北側、太郎山を背にした新田地域に位置し、昭和28年より保育園として開園しました。そして平成31年4月1日より幼保連携型認定こども園の認可をいただきました。
園舎は便利な道路交通網の中に位置していますが、花と緑の自然に恵まれた環境にあります。また、モンテッソーリ教育を教育・保育の柱とし、3歳以上児クラスは、たて割り保育(異年齢保育)を実践しています。その中で、子どもたち誰もが持つ可能性の種が、その成長にふさわしい整えられた環境の中で、自らの意志の力で伸びていけるよう適切に援助していくことを教育・保育の旨としております。

さて、今となれば懐かしさすら感じるコロナ禍の期間。芙蓉園ではあのピンチをチャンスとすべく、教育・保育の見直しを様々に重ねてきました。「教育・保育の中で、目的と手段を取り違えたものがないか常に検証し、これまでの当たり前を見直そう!」と、次の3つの視点から取り組みを始めました。
①子どもの自律、主体性、尊厳を妨げている教育・保育内容はないか?(忙しいなどの理由から、なし崩し的に大人の都合で子どもの主体性を奪っていないか?)
②目的を見失った教育・保育はないか?
③非効率(無駄)なものはないか?
毎年、年度当初に、「職員一人一人が当事者意識をもって、できることから一つ一つ改革改善していきましょう」と呼びかけ、試行錯誤を続けています。大きな部分では、年間行事の流れ、各行事の内容について。日常的な点では、生活の流れ、制作物、連絡帳の書き方など。まだまだうまくいっていない事、課題もたくさんありますが、園内に「ともかくやってみよう!ダメだったらそこでまた考え直そう!」という気風が芽生え、広がってきているように感じています。

今、「主体的な保育」という言葉が業界を席巻していますが、子どもたちが主体的であるためには、前提として、その歩みを支える保育者たちが主体的な仕事の仕方をしているのかどうかが問われると思います。
そうした中で昨年度と今年度を通じて成果をあげているのが、1歳児さんの生活の自立へ向けた取り組みです。モンテッソーリ教育の考え方に則り、改めてその生活を見つめ観察することから始めました。すると私たちが思っている以上に、子どもたちは自分のことを自分でやりたいと思っていることに気がつきました。モンテッソーリ教育では、どんな小さな人であっても、一人の「生活者」として関わることを大切にしています。そう考えてみると、保育者が「よかれと思い」先回りして手を出しすぎていたことが多くありました。ここを根本から見直しました。
今の1歳児さんたちの朝の姿です。朝登園すると、自分で靴を脱ぎ、下駄箱へ入れます。靴下を脱いで、決まった箱に入れ、背負ってきた通園バックを下ろし、机に置いて中身を取り出し始めます。育児日記、食事用エプロン、タオル類、おむつ袋などを、順番に一つ一つゆっくりと所定の場所へ置いていきます。開いたバックの留め具をとめてロッカーへ。家から着てきた上着も、自分の印があるフックへかけます。また食事の際はピッチャーでコップに水を注ぎ、水分補給をします。食後には鏡を見て口を拭き、食器を片づけてお昼寝へ。これらを慎重に、そして生き生きと、かつ淡々と行っていきます。そして最後に見せる満足そうな笑顔。こうした日常の「できた!」の積み重ねが、子どもたちの今を深めていきます。
こうした姿のために私たちが行うのは、環境を整えることです。子どもたちの「やろう」とする意欲が阻害されるものはないか、検討を重ねてきました。こうした視点を、対象年齢を問わず広げていけば、まだまだ私たちができることはありそうです。生活する子どもたちの姿から教わる日々は続きます。
副園長 飯島俊哲
※長野県保育連盟の会報誌『保育しなの187号』(令和7年3月25日)に寄稿した文章です